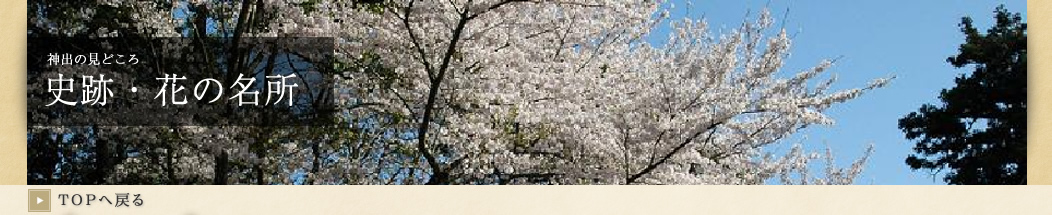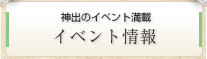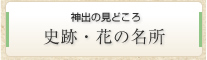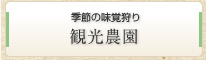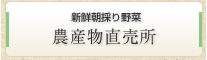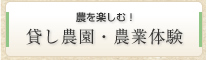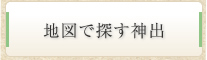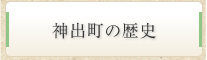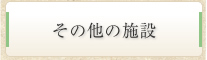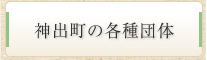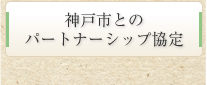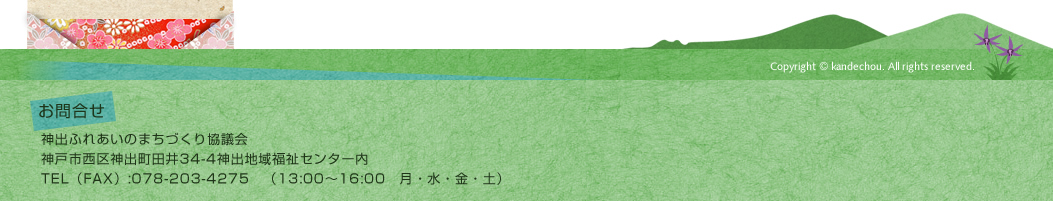平坦な神戸市西区で最も高い山で、標高は249m(ニシク!)。 古代から神が鎮座する山として信仰されてきました。 牛頭天王を祀っていることから"天王山(てんのうさん)"とも呼ばれ、山頂には神出神社が祀られています。『改訂・兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドデータブック2003』の自然景観でCランクにあげられています。また、山頂からの眺望は、『神戸らしい眺望景観10選』にも選ばれています。 入り口の鳥居から山頂までは約1kmで、歩いて20分ほどの距離。健康のために登山する人が絶えず、毎朝登山会も組織されています。 |
 |
雌岡山山頂に所在しています。 素盞鳴命(スサノオノミコト)と妻の奇稲田姫(クシナダヒメ)、および大己貴命(オオナムチノミコト)を祭神としています。後に、前2神の孫にあたるオオクニヌシノミコトから八百余の神々が生まれたことが、「神出」の由来とされています。 |
 |
雌岡山の中腹、山頂の北側に所在する神社。 裸石神社は、彦石という男性を象った大きな石が御神体であり、姫石神社は女性を象徴する三裂した巨岩を祭っています。 |
 |
雌岡山の東側に位置する山で、神出の象徴として"めっこさん・おっこさん"と雌岡山と対で紹介されことがあります。山頂には雄岡神社(祠のみ)が祀られており、五穀豊穣をご利益とした農業守護のシンボルでもあります。 西の雌岡山ほど整備されていませんが、ともにハイキングコースになっています。麓にある金棒池は、怪力無双の弁慶が金棒を雌岡山と雄岡山に突き刺し、持ち上げようとして金棒が折れ、落ちた場所が窪んでできたと言われています。 |
 |
江戸時代、明石藩の城主小笠原、松平、大久保、本多氏など歴代の城主が鷹狩りに来て、休憩をされる"お茶屋"があったことから御茶山と呼ばれています。 |
 |
明治の中頃、神出町小束野の一帯は松林を主体とした原野が広がっていました。 中国で生まれた呉錦堂氏は、貿易商として成功した後、この小束野原野の開拓に力を注ぎました。 現在の小束野の基礎を作った呉錦堂氏を称え、昭和30年頃に地域の重要な水源であるため池(宮ヶ谷池)を"呉錦堂池"と改名しました。 |
 |
北区淡河町から神出町の練部屋分水工までの淡河川疎水、北区山田町から神出町の呉錦堂池までの山田川疎水の二つの疎水の頭文字をとって、『淡山疎水』と言われています。 現在、2,500haの農地を灌漑しています。平成18年に国の"疎水百選"に選定されました。 |
 |
水不足に悩む神出町では、頻繁に水を取り合う争いが絶えませんでした。淡山疎水が完成し、その悩みが解消されたことで平和が成ったとして、地域に中心に位置するため池を『和合成池』と命名しました。 和合成池は、神出町公園・神出自然教育園に隣接し、地域住民や訪れる人達にとっての交流と憩いの場所です。 将来的には、遊歩道や親水空間の整備を行い、神出町のシンボル的な場所として魅力を作っていきます。 |
 |
神出町では、雌岡山山頂をはじめとして色々な場所に桜を植栽しています。 春を彩る桜ネットワークと称して、今後も植栽本数を拡大していきます。開花時期は4月上旬です。 |
 |
雄岡山の中腹には、つつじが群生している場所があります。 5月〜6月頃の満開の頃は圧巻の美しさです。 |
 |
雌岡山の南東の中腹には梅林があります。 3月初旬にかけて美しく開花する梅の花は春の到来を感じさせます。 |
 |
雌岡山にはかつてユリ科のカタクリが群生していました。県のレッドデータブックでCランクに指定されているカタクリは、神出でも見ることが激減しました。 地域の老人会(かたこ会)により、2003年から人工的に移植に励んでいます。受粉を助けるために欠かせないギフチョウの飼育は神出自然教育園が手がけています。 4月中旬にカタクリの鑑賞会が開かれています。 |
 |
平成23年度より、地域内の休耕田の拡大防止策として花畑プロジェクトを開始しています。レンゲ、菜の花、コスモスなど畑を荒らさずに花を植えて地域内外の人の心に潤いを与える企画です。 今後も拡大していきますよ。 |
 |
現在制作中です 神出町の幾つかの地域では、女性グループによる花壇の植栽に取り組んでいます。中には、これまで何回も表彰を受けたグループもいます。季節ごとの花壇を楽しんでください。 |
 |